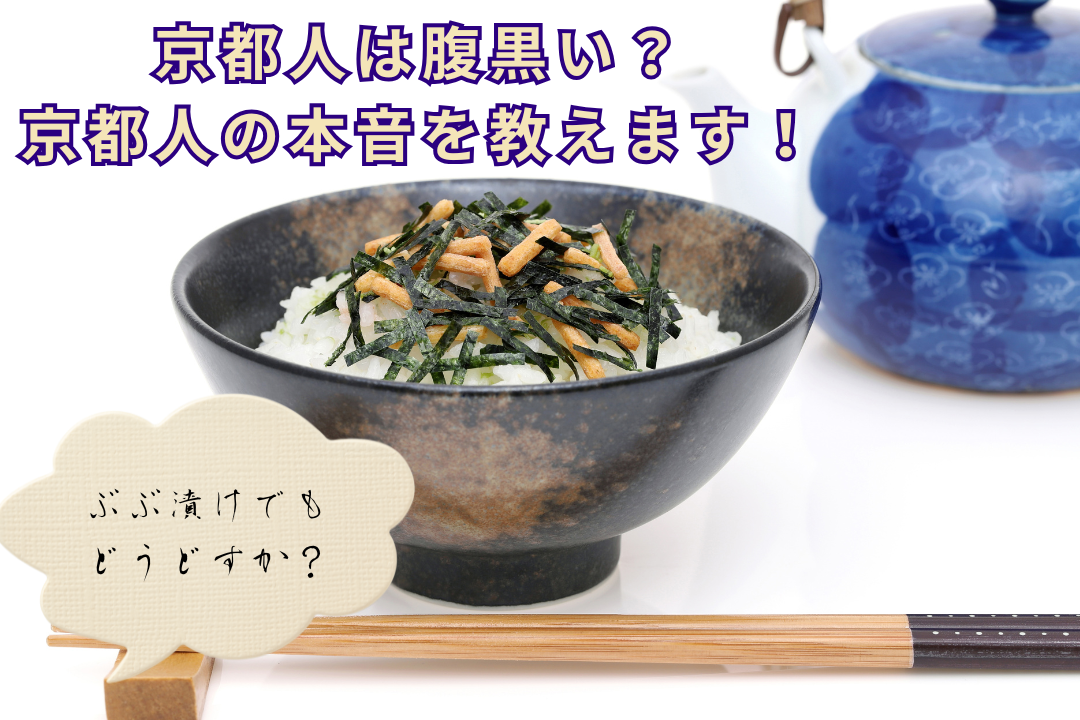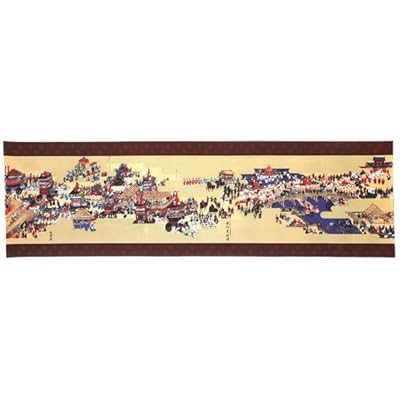「京都みやげ、いつも八つ橋やお漬物でワンパターンになりがち」
「お菓子以外で、もっとセンスが光るおみやげはないかな?」
京都のおみやげは、ついつい無難なお菓子を選んでしまいがち。
しかし、京都にはお菓子以外にも歴史の中で磨かれ、京都の人々に古くから愛用されてきた「本物」の逸品があります。
この記事では、京都人である筆者がお菓子以外で本当に喜ばれる「本物の京みやげ」を12品厳選して紹介します。
職場用や友人へ、そして自分へのご褒美まであなたの目的にぴったりのおみやげが必ず見つかりますよ。
京都みやげにぴったりのスイーツはこちらの記事で紹介しています!
【定番】日持ち・軽さ重視!職場にも喜ばれる京みやげ4選
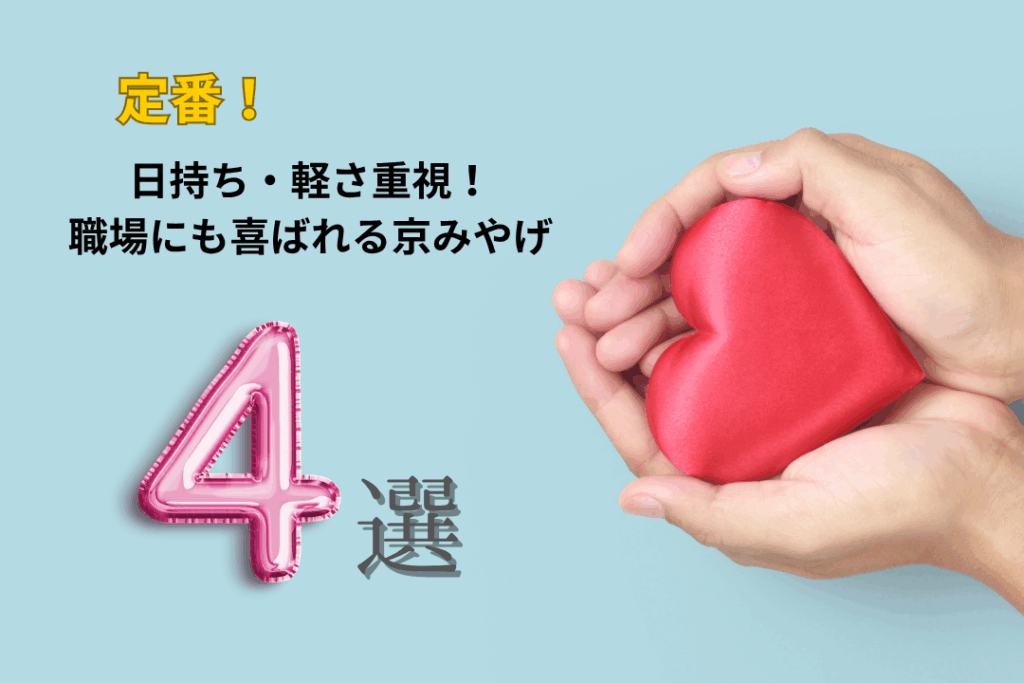
お土産選び、特に職場へは「日持ち・軽さ・京都らしさ」の三拍子が揃っていてほしいもの。
それでいて「センスいい!」と喜ばれる、京都人が自信を持っておすすめする「定番みやげ」を紹介します。
それでは、ひとつずつ詳しく紹介していきますね。
よーじや(コスメ)
よーじやといえば「あぶらとり紙」があまりにも有名ですね。
よーじやは1904年創業。もとは花街のプロに応える舞台化粧道具のお店でした。
当時「楊枝(ようじ)」と呼ばれた歯ブラシを扱っていたことから、「よーじや」という愛称で呼ばれるようになったそうです。
そんなよーじやが扱うあぶらとり紙のルーツは、京都の「金箔」作りにあります。
京都は古くから金閣寺や仏壇仏具、屏風など金箔を使う伝統工芸が非常に盛んな土地です。
その金箔を叩き延ばす際に使われる「箔打紙」は、皮脂を驚くほどよく吸う特性を持っています。
工芸の都・京都だからこそ手に入りやすかったこの紙を、美意識の高い祇園の舞妓さんたちが愛用し始めたのがあぶらとり紙の始まり。
現在よーじやではあぶらとりがみだけでなく、スキンケア商品やフレグランス、雑貨などもラインナップされています。
- 職場や友人への「定番」みやげとして
- 美意識の高い方への「通」なギフトとして
- 渡す相手を選ばない、絶対の安心感が欲しい時に
松栄堂(お香)
京都の「香り」といえば、まず名前が挙がるのが「松栄堂」です。
1705年以来300年以上にわたり京都で香づくり一筋、現在13代目に至る老舗です。
お香は、寺社仏閣でのお勤めに欠かせない「祈りの道具」。
松栄堂はまさに寺社仏閣の御用達として、今も京都の多くのお寺に香りを納めています。
「本物」を扱うからこそ、その香りは別格。
天然の香料でしかつくれない微妙で深みのある「品の良い香り」が、香りに敏感な京都の人々に愛され続けています。
 このか
このか私は自宅で「堀川」というお香を愛用しています!
お香や匂い袋だけでなく、ユニークなお香のカードゲームなども取り揃えています。
- 京都らしい本物の香りでリラックスしたい方に
- かさばらず、品のよいおみやげとして
- 和のテイストや丁寧な暮らしが好きな方へ
京都の住所はちょっと特殊。北へ向かうことを「上ル」西へ行くことを「西入る」と表記する場合があります。
詳しくはこちらの記事で解説しています!
原了郭(黒七味)
京都の薬味といえば、まず思い浮かぶのが原了郭の「黒七味」。
創業は1703年、300年以上にわたり祇園の地で愛されてきた老舗です。
そもそも京都のうどん屋さんでは、七味とは別に「山椒」がよく置かれています。
はんなりと甘めの出汁文化に山椒のピリッとした刺激がアクセント。
それほど京都の食文化と山椒はつながりが深く、好まれてきた背景があります。
看板商品の「黒七味」は、 白ごま・唐辛子・山椒・青のり・けしの実・黒ごま・おの実の7種類を使用しています。
原了郭の「黒七味」は一般的な七味とは一線を画す、まさに山椒の風味を主役にした「和のスパイス」です。
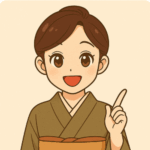
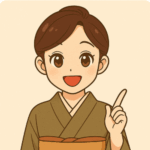
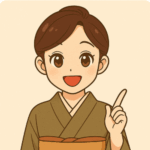
焙煎による香ばしさと山椒の爽やかな香りが、京都のうどんや丼ものにピッタリです。
もちろん、うどんや丼ものだけでなく、ステーキやパスタ、揚げ物など和洋問わずあらゆる料理の風味を格上げしてくれます。
- 料理好きな方への手みやげとして
- 京都の味を取り入れたい方に
- 山椒・和のスパイスがお好きな方へ
一保堂茶舗(日本茶)
京都人がきちんとしたお茶を贈る時に、まず名前が挙がるのが「一保堂茶舗」です。
創業は1717年。幕末に「お茶一つを保ちなさい」という思いを込め「一保堂」の屋号を賜って以来、お茶一筋に歩んできた老舗です。
抹茶・玉露・煎茶・番茶の4茶種・約30銘柄が揃うため、相手に応じて柔軟に選べるのも専門店ならではの強み。
たとえば、茶道をしている人には「抹茶」、気軽に楽しみたい方には「煎茶・ほうじ茶のTパック」、高級なお茶を味わいたいなら「玉露」といった選び方ができます。
ちなみに「京都のぶぶ漬け」では、お番茶と呼ばれるお茶がよく使われます。
お番茶とは、京都では香ばしい「ほうじ茶」のこと。



「おばんざい」の「ばん」と同じで、普段使いという意味があります。
そんな小ネタと一緒に、ほうじ茶のTパックを贈るのも京都らしくておもしろいですね。
京都の「ぶぶ漬け」の意味については、こちらで詳しく解説しています!
- お菓子が苦手な方や目上の方への贈り物として
- 茶道から日常まで、贈る相手の好みに合わせて選びたい時に
- 京都のぶぶ漬けを体験したい方に
【暮らしのアイテム】愛用したい!京を感じるおしゃれな4選


お菓子以外で「京都らしい」逸品を探すなら、日々の暮らしそのものを豊かにしてくれる上質な「暮らしのアイテム」もおすすめです。
使うたびに愛着がわく、京都の美意識が息づく4選。
自分用にはもちろん、センスを褒められる特別なギフトにもぴったりです。
さっそく、チェックしていきましょう。
永楽屋(手ぬぐい)
かさばらない京みやげの代表格といえば、永楽屋の手ぬぐいです。
創業は1615年で400年以上続く日本最古の綿布商として、京都で商いを続けてきた老舗中の老舗です。
400年の歴史を感じる伝統的な柄をモチーフにしたものからモダンで可愛い柄まで、その両方を楽しめるのが最大の魅力。
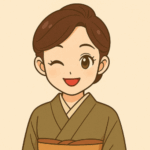
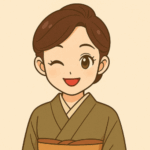
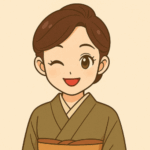
クスッと笑える「舞妓さんシリーズ」が私のお気に入りです!
手ぬぐいは使い方もさまざまです。
ペットボトルやワインボトルを包んだり、ブックカバーにしたり。
ガーゼ手ぬぐいを首に巻いてファッション小物にしたり、お気に入りの柄を額に入れてインテリアにするのもおしゃれですね。
ラインナップは手ぬぐいだけでなく、風呂敷やハンカチ、バッグまで揃います。
- かさばらず、軽くて、センスの良いおみやげを探している方に
- 柄やデザインにこだわりがあり、アートが好きな方へ
- 京都らしいデザインが好きな方に
かづら清老舗(椿油・櫛)


京都の女性の「美髪」を支えてきたのが、「かづら清老舗」の椿油とつげ櫛です。
創業1865年の老舗で、もとは芝居小屋を営むかたわら舞台用の「髪小物」を扱っていました。
看板商品の「つばき油」は、髪はもちろん肌やネイルケアにも使える万能アイテムです。
そして、つばき油と一緒に贈りたいのが「つげ櫛」。
静電気が起きにくく、この椿油を染み込ませて使うことで髪に自然な艶を与えてくれます。
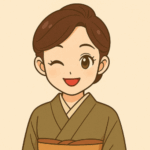
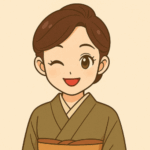
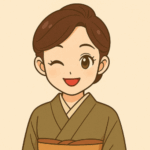
使い込むほどに、櫛自体が美しい飴色に育っていくのも魅力のひとつ。
その品質の高さは、花街の女性や「京都御所」の女官にも愛用されてきた歴史が物語っています。
- 髪のパサつきや乾燥が気になる方へ
- 髪を大切にする、美意識の高い方へ
- 永く愛用し、自分だけの「道具」を育てたい方に
みすや忠兵衛(裁縫道具)
お裁縫好きな方にとって、まさに憧れの道具と言えるのが「みすや針」です。
1819年から「みすや忠兵衛」として針一筋で営み、京都の着倒れ文化を支えてきました。
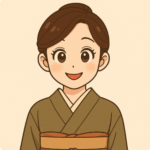
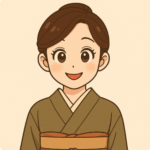
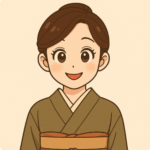
着倒れとは、衣装に財を費やすという京都の美意識のことです。
西陣織や京友禅など上質な絹織物で着物を仕立てる、そのための本物の道具が「みすや針」だったのです。
「本物」たる所以は、そのこだわりの製法にあります。
布地を傷めないなめらかな針先、糸がねじれず通りやすい「まん丸の針穴」、そして布の抵抗を極限まで減らす「縦磨き」の仕上げ。
プロの厳しい要求に応えることで磨き上げられた「針通りの良さ」は、格別です。
伝統的な和裁用だけでなく、刺繍やパッチワーク用など、現代の「縫い人」の思いに応える針も揃います。
美しい「お裁縫セット」は、持っているだけで気分が上がりますね。
自分用として長く愛用するのはもちろん、お裁縫好きな方へ贈るにも喜ばれる、まさに「京を感じる」逸品です。
- お裁縫が好きな方へ、特別な「道具」として
- 「本物」の道具で、日々の暮らしを丁寧に楽しみたい方に
- 小さくても上質なギフトを探している方に
鳩居堂(和文具)
デジタルな時代だからこそ、手紙やメモにこだわりたい。
そんな時に京都人が訪れるのが「鳩居堂」です。
創業は1663年。本能寺の門前で「薬種商」として始まった、非常に歴史あるお店です。
薬の原料を輸入していた中国から、筆・墨・硯・紙といった文具も一緒に輸入して販売したのが、和文具専門店としての始まりです。
京都は、多くの文人墨客が活躍した「学問と芸術の都」。
鳩居堂は、そんなプロたちの厳しい要求に応える本物の道具を扱うことで、その地位を確立してきました。
現在も本格的な書道道具からお土産にぴったりな美しい季節のはがき、一筆箋、和紙小物まで幅広く揃います。
自分用はもちろん目上の方へ贈るにも喜ばれる、まさに京都らしい逸品です。
- 手紙やハガキなど「書くこと」が好きな方へ
- デジタル時代だからこそ、手書きの「温かみ」を大切にしたい方に
- 京都らしい小物を探している方
【京の伝統工芸】本物志向!暮らしを格上げする逸品4選
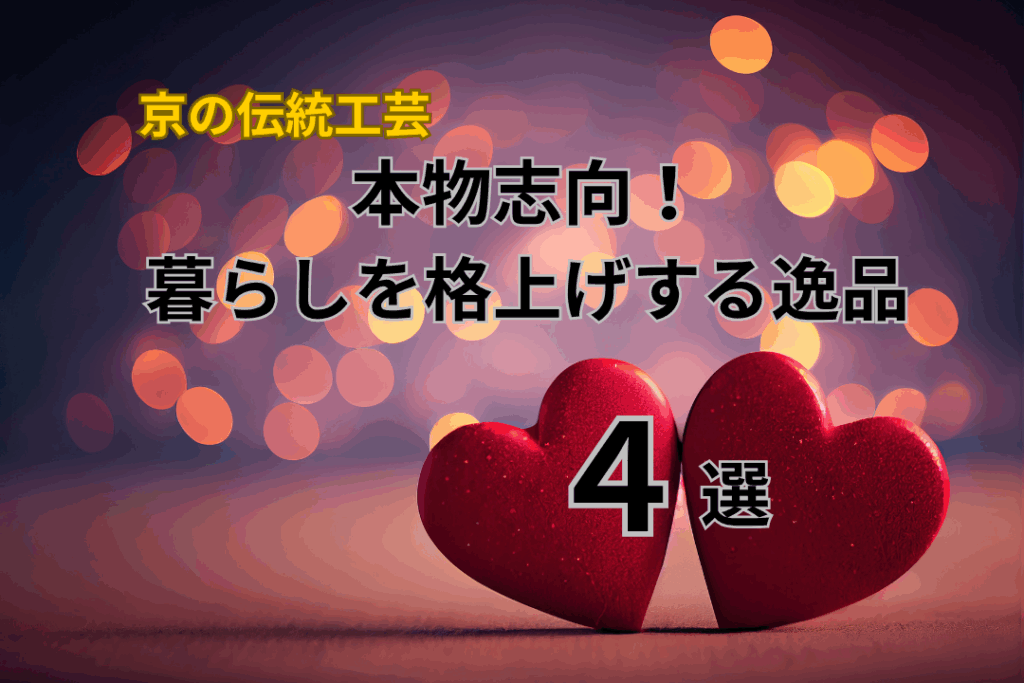
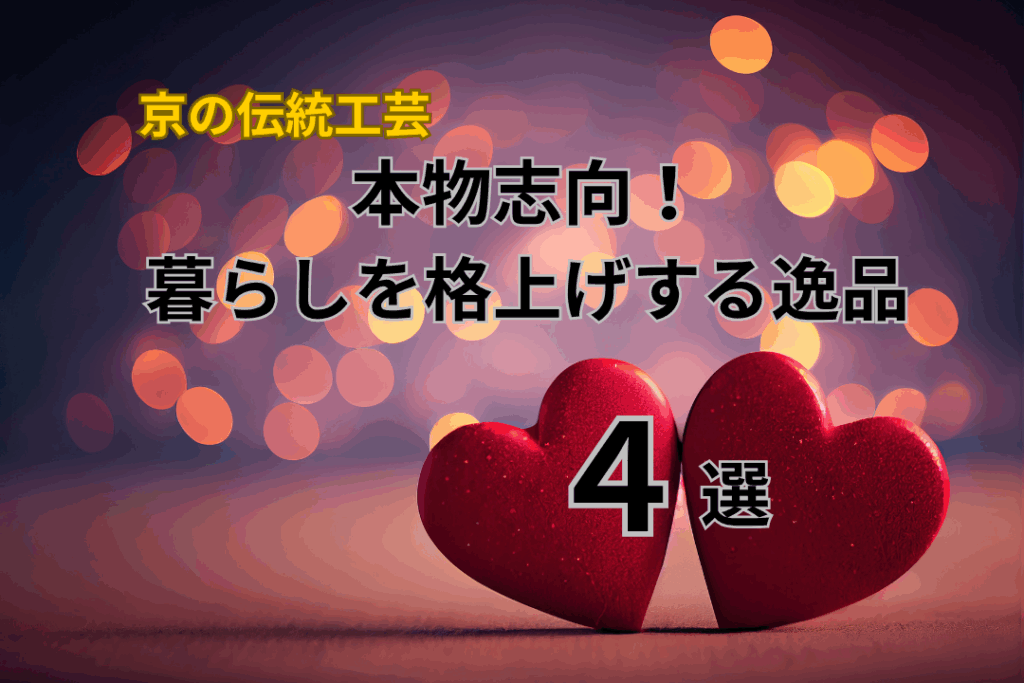
今までの「京みやげ」から一歩踏み込み、まさに「本物志向」のおみやげを探しているあなたへ。
日々の暮らしを確実に「格上げ」してくれる、京都の職人技が光る「伝統工芸」の逸品を4つ紹介します。
自分への「一生モノ」のご褒美として、また大切な方への特別な贈り物として、ぜひ手に取ってみてください。
辻和金網(茶こし・焼き網)
「自分ではなかなか買わないけれど、貰ったら心から嬉しい」 辻和金網の道具は、まさにそんな「丁寧な暮らし」を象徴する逸品です。
京都の金網の歴史は平安時代に遡ります。その技を受け継いだ職人たちによって明治以降、金網工芸は盛んに作られるようになりました。
しかし、戦後に安価なプラスチック製品が登場すると、手仕事の金網は次々と姿を消していきます。
そんな中でも辻和金網が本物として愛され続けるのは、機械では真似できない職人の手仕事による「雅」があるから。
指先の感覚だけを頼りに編み込む網目の美しさは、料亭のプロも愛用する用の美そのものです。
手編みの「茶こし」はもちろん、トーストがふっくら焼ける「焼き網」や和モダンな「コーヒードリッパー」も人気。



長く使ってほころびが出ても修理して使えるのも、一生モノの道具ならではですね。
日々の暮らしを確実に「格上げ」してくれる、本物志向のあなたにこそふさわしい逸品です。
- 「丁寧な暮らし」に憧れ、良い道具を揃えたい方へ
- 日々の「ひととき」を大切にしている方へ
- 修理しながら「一生モノ」として使える道具を探している方に
有次(包丁・型抜き)


「有次」の包丁を手にすることは、450年以上の「刃物の魂」を手にすることといっても過言ではありません。
1560年の戦国の世に「刀鍛冶」として創業し、京都御所の御用鍛冶を務めたという桁違いの歴史を持ちます。
泰平の世と共にその「刃物」の技術は、刀から仏師用の小刀へ、そして「料理庖丁」へと遷っていきました。
有次は「京の台所」錦市場に店を構え、京都の料理人たちの厳しい要求に応え続けてきた本物の道具です。
その切れ味は抜群で、食材の繊維を潰さず素材本来の旨味を引き出してくれます。
「良い道具は人の技を引き上げる」というのが、有次の信条。
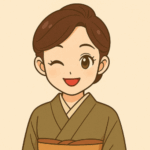
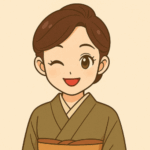
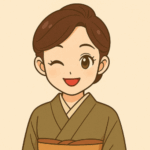
包丁はまさに「一生もの」です。
お手入れは必要ですが、その分だけ愛着が湧く、まさに「育てる」道具です。
包丁はもちろん、桜や紅葉といった季節の「抜き型」や「卸金」も、日々の料理を格上げする逸品です。
- 料理を愛する全ての方へ、最高の「相棒」として
- 「一生モノ」の道具を、手入れしながら育てたい方に
- 季節の料理(型抜き)など、食卓の「美意識」にこだわりたい方へ
中村商店(和ろうそく)
中村商店の創業は1887年。
もとは仏事などに使われてきた和ろうそくの伝統を守る、京都でも数少ない専門店です。
お寺が非常に多い京都では、古くから仏事にろうそくが欠かせません。
原料がすべて植物性で油煙が少なくお仏壇を汚しにくい和ろうそくは、まさに「お寺の都・京都」ならではの必需品でした。
和ろうそくは芯が空洞になっているため空気が流れ、炎が「ゆらゆら」と大きく揺らめくのが特徴。
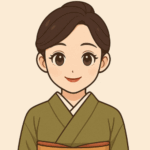
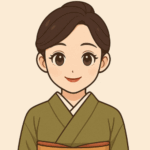
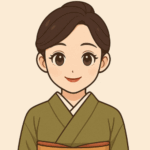
その神秘的な揺らぎは、見ているだけで心を静かにしてくれます。
最近の和ろうそくには、美しい絵柄が描かれたものも。
この「絵ろうそく」は、火を灯さずお花の代わりとして「飾る」ためのお供えとしても使われます。
揺らめく炎で心を癒したり、美しい絵柄で空間を彩ったり。 きっと日々の暮らしを格上げしてくれるでしょう。
- ゆらゆら揺れる「炎」で、夜のリラックスタイムを豊かにしたい方へ(和蝋燭)
- 火を灯せず「飾る」、美しいインテリアや贈り物を探している方に(絵蝋燭)
- 日本の工芸品に興味がある方への贈り物として
白竹堂(京扇子)
お菓子以外の京みやげで、最も粋で実用的なのが「京扇子」です。
「白竹堂」は1718年、西本願寺の門前で寺院用の扇子を扱う「金屋孫兵衛」として創業した老舗です。
そもそも「京扇子」とは、扇面・扇骨・仕上げの全工程を京都・滋賀を中心とした国内で生産した扇子のこと。
「京扇子」という名称は、京都扇子団扇商工協同組合の組合員だけが使用できる「本物」の証です。



約88もの手仕事の工程を専門の職人たちが分業することで、あの優美な扇子は生まれます。
そして何より扇子は「末広」とも呼ばれ、その形から「繁栄」を象徴する非常に縁起の良い贈り物となります。
白竹堂はそんな伝統を守りながらも、刺繍やラメプリントが施されたものや伝統柄を現代風にアレンジしたものなど洋装にも合うモダンなデザインも豊富。
さらにお名前の彫刻も可能で、世界に一つの特別なギフトになります。
自分用にはもちろん、目上の方へ「末広がりの福」を贈る、最高峰の京みやげです。
- 夏の「涼」を粋な「本物」の道具で取り入れたい方へ
- 「末広がり」の縁起物として、お祝いや目上の方への贈り物に
- 「名入れ」で、世界に一つの特別なギフトを贈りたい方へ
次の京都旅はお菓子以外で「本物」の京みやげを選ぼう!
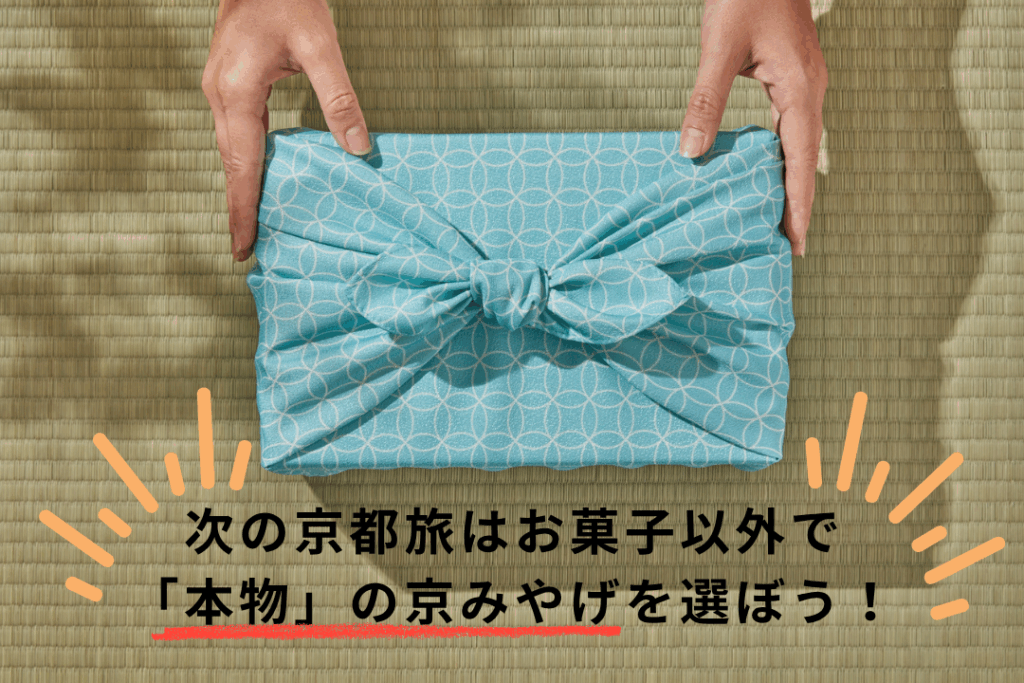
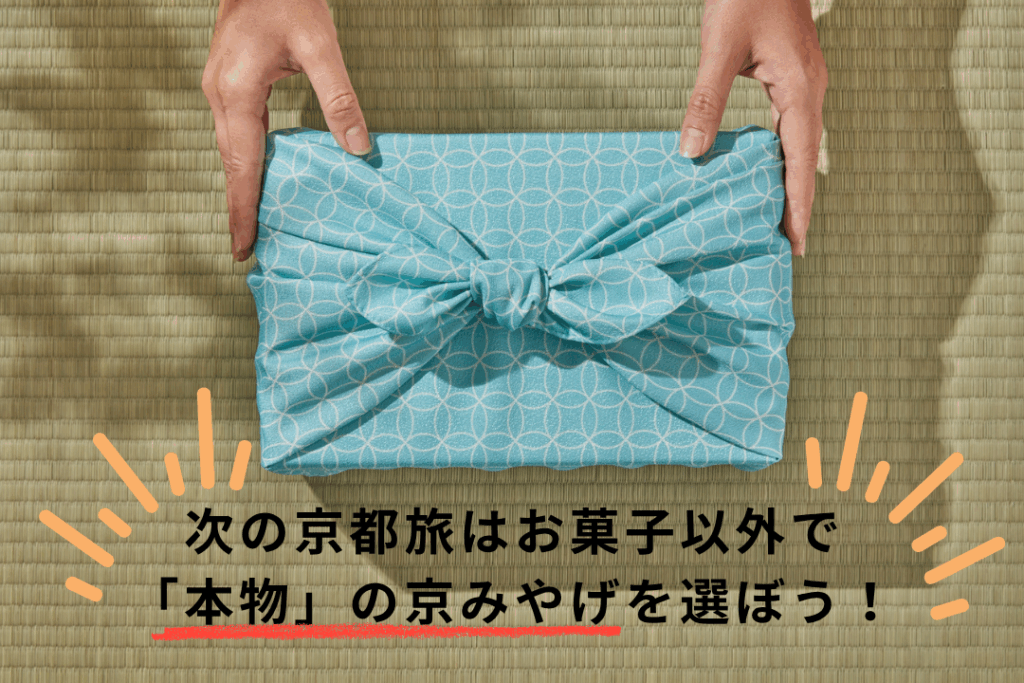
京都人である私の視点から、お菓子以外の「本物」の京みやげを12品、3つのテーマに分けて紹介しました。
日々の「定番」を格上げしてくれる逸品から暮らしを豊かにする「アイテム」、そして「伝統工芸」の逸品までどれも京都の歴史や文化に深く根ざしたものばかりです。
この記事を通して、京都のおみやげ選びがもっと楽しく、もっと奥深くなる「5つのヒント」をまとめます。
- お菓子以外にも、京都の魅力的な選択肢は無限にある
- 「本物」には、京都の歴史や職人技という「物語」が詰まっている
- 「本物」のアイテムは自分用に「愛用し、育てる」楽しみがある
- 持ち帰った後も、日々の暮らしを格上げしてくれる
- 「本物」を選ぶ体験そのものが、京都旅をより豊かにする
ありきたりの「おみやげ」で済ませる旅は、もう終わり!
次の京都旅では、ぜひあなただけの「本物」の京みやげを見つけてみてくださいね。